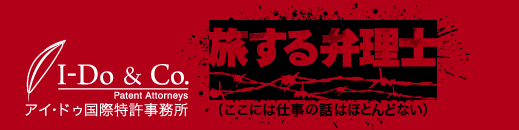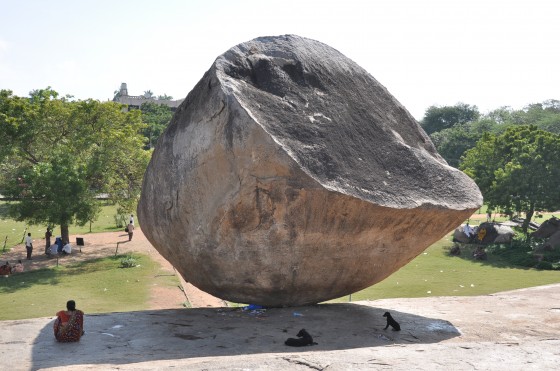その翌日。朝、連続的な物音で目が覚める。窓の外に目を向けると、まだ薄暗かった。しかし枕元の時計は8時を指している。この物音は何か、なぜ薄暗いのか。雨だ。しかも、大雨だ。ケーララの12月は年間降水量が最も少ない月であって、一般的には乾季と呼ばれる時期にあたる。やれやれ。雨男の本領発揮である。いや、むしろ乾季の南インドに雨を降らせたとなれば、ただの「男」というより、むしろ「神」の領域に近づいてきているのかもしれない。雨神様の誕生である。
大好きな街歩きもできないので、部屋でゴロゴロしながら小説の頁をめくった。雨が降っても、当然の如くお腹は空く。昼過ぎに意を決し、大雨のなか近所のお菓子屋でドーナツとチャイを立ち食いして、また宿に戻ってゴロゴロしながら小説の頁をめくる。結局、雨に止んでいただけたのは、昼の3時を回った頃だった。

雨上がりのフォート・コチを散歩する。ひんやりとした空気が心地よい。昨日歩いて楽しかった下町の方へと足を向けてみる。雨が降り止むのを待ち侘びていたのは人だけじゃなかったようで、遊び相手を求めていたのかネコが2匹こちらに向かってやってきた。人恋しい者同士、1人と2匹でじゃれ合う。

住宅の集まる細い路地を歩いていると、親父ばかりが数人集まっている小屋を見つけた。気になってその前をうろうろしていると、中から手招きされるので思い切って中へ足を踏み入れる。そこにあったものは、なんと、カロムだ。

知る人ぞ知る幻のゲーム、「カロム」。ただし、幼少時代を滋賀県彦根市で過ごしたものなら誰でも知っている、「カロム」。木製のコマを指で弾いて別のコマに当て、それを四角のポケットに落とす、要はビリヤードの原型である。なぜか日本では彦根市でしか残っておらず、その特異性は多くのマスコミ等にも多く取り上げられている。私は小学校時代を彦根で過ごしたので、もちろんルールも完璧にわかっているし、全国大会(彦根市限定)への出場経験もある(すぐに負けたが)。インド人の親父にこれを何と呼ぶのかを聞くと、はっきりと「キャロム」と答えた。ああ、まさか20年ぶりにこんなところで出会うことになるとは。

ということで、早速プレイ。日本(彦根)のカロムと違って四角のポケットが小さく、それはコマの直径を一回り大きくした程度だ。これは相当正確なショットが要求されるため難易度が高い。ダブルスでプレイしたのだが、一緒に組んだおじいちゃんの大活躍により驚くべきことに勝利を収め、負けたチームの親父に隣の店でチャイを奢ってもらった。次回は、ぜひ日本チャンピオンとケーララチャンピオンとで対戦していただきたいものだ。

日が暮れるまで下町をふらふらと散歩する。このあたりはモスクが多く、一斉に鳴り響くアザーンが耳に心地よい。そして、昨日よりも街を歩く人が多いような気がする。はしゃぐ子供たちも雨で溜まったフラストレーションを一気に吐き出しているようだ。そういえば、この日は大晦日だった。



晩飯を食べようと思い、トルコ風のケバブを売る軽食屋の前で並んでいると、偶然、大人数のパレードに遭遇した。白装束を来た男が先導し、巨大な十字架がつき、その後ろに一般の人達が永遠と列をなしている。Santa Cruz Basilicaと書かれた垂れ幕が掲げられていたので、昨日行った美しい教会を中心とする人々であることはすぐにわかった。総勢500名はいるだろうか。慌ててケバブを受け取って、手に持ったままパレードを追いかけた。

パレードの前半は厳かに歩いているだけだが、後方には上半身裸で太鼓を叩きながら踊る一団があり、なんと最後尾にはマリア像のようなご神体を乗せて音楽を流すサウンドカーまで擁している。キリスト教がインドに渡って現地の色に染められて信仰が守られるのは理解できるのだが、サウンドカーの流す音楽は、きっと、それは賛美歌なのだろうけど、実際にはヒンドゥー歌謡にしか聞こえない。まあ、それでもいいじゃないか。

最後尾からケバブを頬張りながら追いかける。道の両側の家々から、ニューイヤーを祝う花火が一斉に焚かれた。カラフルな火花と立ち上る煙の中、太鼓は打ち鳴らされ続け、踊りは激しさを増していく。フォート・コチの街をぐるりと回って、Santa Cruz Basilicaに戻って一行は教会の奥へと消えていった。宿に戻る途中にも、ごく普通の民家からダンスミュージックが大音量で流れている。もうすぐ日付が変わり、新しい年を迎える。この日この時間のフォート・コチに、眠りの気配は全く感じられなかった。