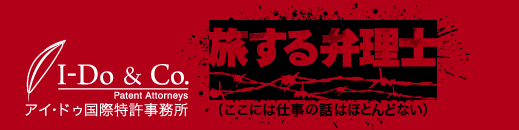ハバナ旧市街は、植民地時代にアメリカの国会議事堂を模して建てられたCapitolioが中心となる。これは街の目印として非常にわかりやすい。迷子になっても、タクシー乗っても、スペイン語が多少不自由でも、「きゃぴとりお!」と叫べば、まあ何とかなる。
宿は、Casa Particular(キューバ版民宿、というよりは、むしろホームステイに近い安宿)が旧市街にいくらでも転がっているので、2~3軒回って好きなところに落ち着けばいい。一応、Lonely Planetで目星をつけていったが、それは全く不要であった。ガイドブックには出てこない素晴らしいCasaがいくらでもあるのだ。空港からのタクシーをキャピトリオ前で降りて、たまたま捕まった客引きは、全身白の服にサングラスという胡散臭いダンスホールレゲエシンガーといった様子だったが、陽気な彼に連れられていったCasaは、Capitolioから歩いて3分位の旧市街のど真ん中。親切なお母さんと、朴訥としたお父さんと、セクシーなお姉さんと、その息子の糞ガキの住む素敵なお家であった。テレビやパソコン等の電化製品も充実していて(iPodまであって!)意外と裕福そうだ。そもそも、Casa Particluarは政府によって厳格に管理されていて、ある程度は裕福な家じゃないとライセンスが与えられないらしい。観光産業を重視する方向に舵を切ったキューバにとって、外貨は非常に貴重であり、「持つ者」がより「持つ」ようになる。社会主義国であるキューバを取り巻くその矛盾には、この旅で何度も出会うことになった。
さて、旧市街を歩いてみる。数百年前のコロニアル時代からほとんど変わらないだろう建物がひしめき合い、その間をアメリカン・グラフィティなクラシックカーが走りまわる独特の風景。キャピトリオからカテドラルに通ずるオビスポ通りは観光客でごった返している。観光客嫌い(自分も観光客のくせに)の私ではあるが、なぜだかこの街では嫌な感じを受けない。旧市街にはオープンなカフェやバーが点在している。カテドラルの近くのカフェでモヒートを飲んでいると、流しのミュージシャンがやってきて、ギターとマラカスとボーカルで1曲演奏してくれる。当然、素晴らしい演奏に対してチップを払う。
チップについて。キューバは二重通貨を採用し、外国人向けの通貨(CUC)と現地用の通貨(CUP)が分かれていることは有名な話だ。1USD=1CUC=24CUPで(ちなみに米ドルを両替しようとすると追加手数料がかかるので、カナダドルかユーロの方がいい。とにかくいろいろややこしい)、タクシー、レストランや缶ビール、モヒート等は全てCUC払いとなる。CUPは、現地用の安食堂や屋台等で使える。キューバ人がCUPだけで生活を送ることができればなんら問題はないのだろうが、例えば、缶ビールはキューバ国内で作られているにも関わらずCUCでないと買えない(ただし、CUP用の生ビール屋はあった!)。CUCとCUPとの間の格差がどんどん広がり、そしてCUCの力が強くなり過ぎている。Casa Particularもそうだが、現在のキューバで裕福になるためには、CUCをいかに獲得するかによる。理系の大学を出るような優秀な人材がわざわざタクシーの運転手になるという話を聞いた。給料に格差がないキューバでは、エンジニアよりも、観光客からチップを貰える仕事の方がもうかるらしい。キューバの社会には、一刻も早く解決しなければならない問題が非常に多く、且つ根深い。
だから、彼らは外国人を見かけたら、缶ビール奢ってくれよ、と言う。そして、僕は親切にされたり仲良くなったりしたら、彼らにビールを奢って一緒に飲む。どこの国の、どんな人でも、ビールぐらい腹いっぱい飲む権利くらいあっていい。少し濃いめのBucaneroは、カラッとしたキューバの気候にも、カラッとしたキューバ人の性格にも、非常によく合っていた。